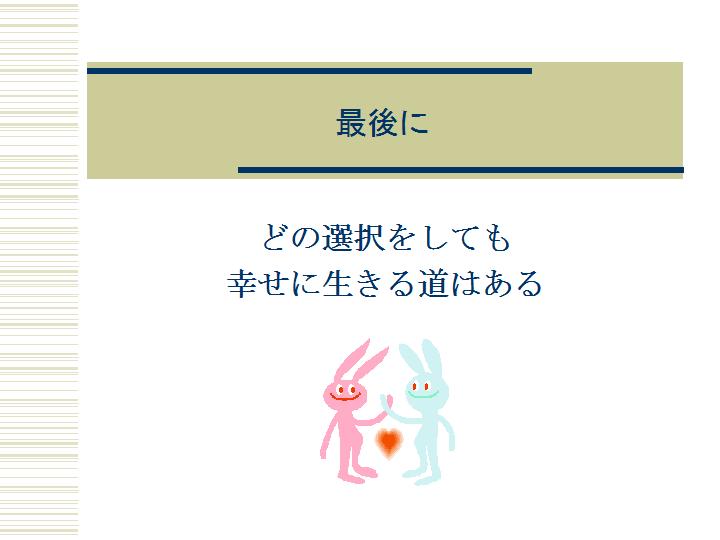命のたすきをつなぐ
週刊現代4月27日 5月4日号「美しく逝きたい」より

山梨県で「ふじ内科クリニック」を運営する在宅ホスピス医の内藤いづみ医師は、美しい最期を迎えるのは「命のたすき」を渡すことができた人だ、と指摘する。どういうことか。
「増田さん(仮名)という肺がんで70代後半で亡くなった女性がいましたが、彼女は病院での標準治療を受けずに、家族とともに自宅で最期の時間を過ごす選択をされました。結局一度も入院せず、約2年間ご自宅で過ごされたんですが、家族に向かっていつも『最期の時間を、こうしてみんなと過ごせて私は幸せだよ』とお話ししていました」
内藤医師は、増田さんが亡くなる数日前の夜のことを鮮明に覚えているという。「ご自宅には娘さんやお孫さんたちがいて賑やかでした。その晩、娘さんたちがカレーを作っていました。すると増田さんがすっと起きて『なんかいい匂いがする』と言うんです。その後お孫さんがやってきて『おばあちゃん、食べる?』とスプーンでカレーを差し出す。増田さんは一口舐めるだけで食べられはしなかったんだけど、嬉しそうに『美味しかったよ』と伝えていました。結局これが彼女の最後の食事になったんですが、なんて幸せな『最後の晩餐』だろうかと思いました」

最期は無理に治療を受けず、家族とともに過ごすと決めたからこそ得られた幸せ。内藤医師は「増田さんは穏やかに亡くなりましたが、ともに過ごした家族が得たものも多かったと思います」と続ける。
「亡くなるまでの数日間、娘さんだけでなくお孫さんたちも増田さんと一緒に過ごしていました。そういう時間を過ごすと、亡くなった瞬間は家族も深い悲しみに包まれるんですが、『お母さんらしい最期だったね』とか、『おばあちゃんと最後にカレーを食べたね』とか、死に向き合った家族には美しい思い出が残るんです」
身内や友人の死に向き合った人は、喪失感と悲しみを抱く一方で、その体験から自分の人生や死についてしっかりと考えるようになるという。内藤医師はこれを「命のたすき」と呼んでいる。
「人生の最期の瞬間は、選べるわけではありません。しかし、元気なうちに少なくとも誰かに「命のたすき』をつなぐための準備はしておくべきでしょう。
家族、あるいは友人知人に、自分がどんな最期を迎えたいかを告げて、人生の終盤を見届けてもらう。その過程を見た人は、決してあなたのことを忘れません。そして、その人自身が自分の人生を考えるようになる。こうして命のたすきを誰かにつなぐことこそが、『見事な最期』を迎えるために必要なんだと思います」
前出の桂歌春さんも原田喧太さんも、大切な人の死に接し「命のたすき」を受け取ることで、人生について見つめ直すきっかけを得た。喧太さんが言う。「僕にも子供がいますが、死を見届けたことで初めて『自分が子供の頃、親父はこう考えていたんだろうな』という考えがわかるようになりました。そして、芳雄と同じように、自分なりの目標を持った人生を送りたいと思うようになったんです」
「美しい最期」を迎えた人たちは、莫大なおカネを持っていたわけでも、そのために多大な時間を費やしたというわけでもない。彼らに共通していたのは、「亡くなる瞬間までこうありたい」という意志を伝えたこと、そして、自分の最期の瞬間を誰かに見届けてもらったことだったのだ。