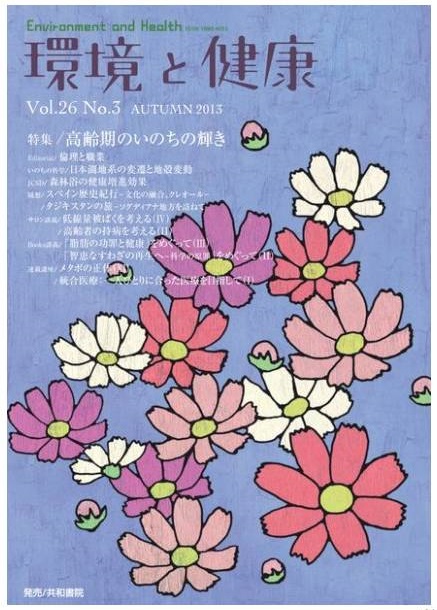いのちとこころの時代を生きる
 (たぶん今日だけ新聞2010年4月10日より抜粋)
(たぶん今日だけ新聞2010年4月10日より抜粋)
内藤いづみさんとの出会いは、1996年の秋、甲府市内のホテルのロビーだったと記憶している。いづみさん(最初から「いづみさん」と呼んでいる。内藤さんでも、先生でもない)は、ピーンと背筋を伸ばし、スックと大地を踏みしめて立っている人、という印象だった。ネイティブアメリカン風に呼ぶなら、さしずめ「風に向かって立つ女といったところであろうか。
風に向かって立つ女!?
背筋が真っ直ぐな人、という第一印象は、いまもって変わらず、それは、いづみさんの医療哲学にも現れている。ぼくらは、編集者であるとか著者であるという立場を越えて、瞬く間に意気投合した。互の理念をぶつけあったFAXは、1年間に段ボール1箱を優に超えた。それが、14年間で6冊の本として結実した。
FAXがメールになり、ぼくがいささか年老いた以外は、いづみさんの意気軒昂ぶりは現在も変わらない。
心の声を聴く聴診器
とある日のこと。たまたま応対した電話の向こうから「関西医科大学心療内科の中井と申します。突然ですが、私の本を出して下さいませんか」という依頼…。
中井教授によると、内藤先生から送られてきた本がとても気に入り、その出版社がオフィスエムだと知り、早速、電話を差し上げたとのこと。単刀直入な用件の割には、その穏やかで腰の低いお話ぶりに好感をもった。
ほどなくして、京都で中井先生とお会いすることになった。夕食後、冬の夜の京都を先生と散歩した。散歩が終わったとき、出版も決まった。出版が決まる時なんて、意外とこんな調子で決まったりするものである。これは、著者と編集者の相性のようなものである。中井先生が言われるように「人生に偶然という出会いはない」のかもしれない。
以前、他の用件で先生と電話で話していた折、ぼくが、つい自分の体の不調ぶりを口にしたら、突然、先生の問診が始まった。その問診は20分にも及んだ。先生は、それまでと変わらない穏やかな口調で、診断を下された。その病名を聴いた瞬間、胸に落ちるものがあった。病名が分からないことの不安から解放された。それから、しばらくして京都の先生の診察室で実際に診ていただいた。診察室には仄かにお香の香がただよっていた。
静かで丁寧な診察は、これまでの診察に対する思い込みを一変するものだった。これほど聴診器を丁寧に扱う医師を他に知らない。まるで、心の襞の音まで聴き取られているようにも思えた。
その夜、フランス料理をご馳走になった。レストランで、先生ご自身が実践されている相撲の四股(しこ)の踏み方を教えてもらった。フレンチレストランで、患者に四股を処方する医師を他に知らない。言うまでもなく、ぼくの病気は一気に快方に向かった。
「鬱の時代」を診る2人の医師
パソコンばかりを覗き込み、患者に触れようともしない医師が増えている。
その貧困なボキャブラリーに驚嘆する。言葉が患者に届いていない。患者の心には、言いようもない不安だけが増幅していく。
中井医師と内藤医師の共通項は、本当の言葉を知っていることにある。それは深い教養に裏付けられているからこそである。患者と真っ直ぐに向かい合い、その言葉によって、多くの患者が励まされている。名医の処方箋は共通している。それは「信頼」という一語であろう。
多くの人々が、格差社会の波に晒され、自己責任という縛でがんじがらめにされている。年間の自殺者が3万人を超えいるこの国は、まさに「鬱の時代」を彷徨っている。だからいま、中井、内藤両医師が「鬱の時代」を診察することの意義は深いはずだ。