悔いなく死にゆくための患者時間・家族時間
生きる意味を深耕する月刊誌「MOKU」2016年4月号より
もしもがんに侵されて余命告知をされたら、残された時間をどう過ごせばいいのだろうか。 最後まで医療にすがるべきだろうか、人生最後の役割を探すべきだろうか。 〝正解〟なんて分からないけれど、〝その日を悔いなく迎えること〟ならできるのではないだろうか。
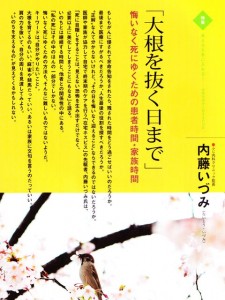
医師や家族が協力して自宅で終末期のケアを行う「在宅ホスピス」の先駆者、内藤いづみ氏は、 「死に目隠しをすることは、見えない恐怖を生み出すだけでなく、 必要以上に美化してしまうことにもなる」と語る。 いのちとは継続する時間と、他者との関係性の中にある。 「私の死」はその中のほんの一部分でしかない。 悔いなく死にゆくための方法も、そんなに難しいものではないようだ。 キーワードは〝自分がやりたいこと〟。 大根を育てるのもいい、麻 マー 雀 ジヤン や競馬だっていい、あるいは家族に文句を言うのだっていい。 肩の力を抜いて、自分の周りを見渡してみよう。〝いのちを支えるもの〟が見えてくるかもしれない。
末期の酒で生き返って 十日間の大宴会!
ある肝臓がんの患者さんのお話です。彼は東京で四十年近く働き、定年を前にふるさとに家を建てました。これからは畑仕事をしながら夫婦水入らずで過ごそうと考えていた矢先にがんが発覚した。余命告知をされ、それなら家で過ごしたい、と考えた。
私が初めて往診した日、畑に大根の種を蒔いている彼に、「先生、収穫まで生きられるかな」と尋ねられ、「そうですね、一緒に食べましょうね」としか答えられなかったことを覚えています。
それから一カ月間ほどは安定していたのですが、ある朝吐血。患者さんは「ここ」で死ぬと言い張りましたが、逆に言えば騒ぐだけの元気が残されているということ、まだ頑張れます。「まだ大根も一緒に食べていませんよ!」と説得し、近くの病院に緊急入院してもらいました。何とか持ち直したのですが、ベッドに手を縛られて体中管だらけ。ただ天井を見つめているしかない状況でした。本人は帰りたいと言いますが、病院の医師はリスクが高過ぎると反対。それでも「残された時間は尊いんです。本人も家族もリスクは承知している」と強引に退院させてもらいました。
またしばらくは平穏な日々が続き、ついに収穫の日がやって来ました。自分で大根を抜いた彼の誇らしげな顔を、いまも忘れることができません。こんなゆったりとした生活を十年、二十年と送りたかった。その願いは残念ながら叶わないけれど、ささやかながら夢は実現しました。
だんだんと症状は進み、ある日意識がなくなりました。誰もが覚悟を決め、昏睡状態のまま五日間ほど過ぎた頃、娘さんから「『末期の水』というのがありますが、父はお酒が大好きだったので、『末期の酒』をあげてしまいました」と電話がありました。しばらくすると今度は訪問看護師から「先生大変です! 患者さんが目覚めました!」と連絡が。娘さんがワインを口に含ませたらゴクンと飲み込んで、少しずつ目が開いてきたそうです。こんなことが起こるなんて!(笑)。
私もご自宅に行って「五日間昏睡状態だったんですよ。何か覚えていますか?」と聞くと、川のほとりにフェリーが停まっていて、人がいっぱい乗っていた。船長が十日前に死んだ僕のいとこ。変だなあと思いながら乗ろうとしたら、お酒のいい匂いがしてきた。
そうだ、一杯飲んでからまたここに来ようと思ったとき、目が覚めたんです」。患者さんの肩をバンバン叩きながら笑ってしまいました。お酒を飲んで生還したのだからと、私もお祝いにウイスキーを持参して乾杯しました。こんなこと病院では絶対にできませんよね。
しばらくすると患者さんのご友人がいらっしゃいました。五日間も昏睡状態が続いていると聞いて「そろそろかな」と喪服で来てしまった。そうしたらなんと酒盛りをしている(笑)。さぞかし驚かれたことでしょうが、結局宴会に加わることに。「嗜む程度に」という忠告もあまり効果はなかったようです。
翌日からも日替わりで友人知人が駆けつけ、昔話に花を咲かせて大宴会。そして十日目の朝、「ちょっと犬の散歩にいってくるね」と出掛けていく奥さんに向かって、「うん、俺は少し眠るよ」と。これが夫婦の最後の会話になりました。信じられない十日間は、神様のプレゼントだったのだと思います。
人生を過ごす場所は 病院とは違う所
病気に限らず、人間にはどんな困難でも乗り越える力があるのだと思います。しかしその道は自分で選んだものでなければいけません。自ら情報を得て、考えて選び、実行することでその過程や結果を愛することができる。これが困難に立ち向かうための原則です。
先ほどお話しした患者さんは、在宅でも最期を迎えることができるという情報を得て、自分で家に帰ることを選び、リスクを冒してでも自分のやりたいことをやった。だから悔いのない最期を迎えることができたのだと思います。
何も終末期医療は在宅であらねばならぬと言いたいわけではありません。患者さんが選んだ場所や治療法を尊重したいと思います。しかし現代の医療ではその選択肢自体が与えられないのです。かつて病院でなければ最期を迎えられなかった時代から、急に国の方針が変わり、在宅医療が推進されるようになりました。治療の手立てのない患者さんはなるべく早く退院になる。
それまで滅多に回診に来なかったのに、「いつ退院できますか?」と毎日詰問するような医者もいる。治療のための入院であっても、最初から退院の日が決められていて、がん手術から五日後には退院させられるなんてこともあります。治療の技術革新の成果や致し方ない側面もあるのでしょうが、もうちょっとゆっくりさせてあげられないものかと思います。
そうした人たちの受け皿となる施設やそこで働く人が足りず、困っている自治体がたくさんあります。特にお年寄りの問題は深刻で、一人暮らし、老老介護、施設に入るための経済的な支障もあります。一方で、私が在宅医療の講演会などをしていても、いまだに「在宅で看取るなんて可能なんですか?」と聞かれます。病院ではない所で死ぬということに対する理解や準備がまだまだ足りない中で、強引に在宅や施設に移行したところで、患者さんは安らかな時間を送れません。
私たちが行っているような在宅ケアの働きやグループホームなどの施設が広がっていくことと同時に、退院のあとのワンクッションも必要です。病院の中に一時的に過ごすことのできる病棟をつくるなり、地域包括ケア病棟を増やすなり、患者さん本人に考えてもらうための場所を造らなければいけない。
同時に日本人一人ひとりの意識も変わっていってほしい。病院は病気を診断し、高機能な機械や専門家によって病気を治す場所、人生を過ごす場所は別にあるのだ、と捉 とら え直す。とにかく病院だ、ホスピスなんて不吉だ、としか考えないのは逆効果だと思います。
病院のあとの受け皿があることを知らなければ、治療を受けることも不安になるのではないでしょうか。「誰だっていずれ死ぬのだから、いずれホスピスという選択肢を選ぶこともあるかもしれない」くらいの気持ちで考えればいいのです。
「お墓の中からお花見ね」 と言える日常を
人生の最期をどのように過ごすべきなのか。「世界一周旅行をしたい!」という人もいるでしょうが、それは元気な人の発想かもしれませんね。実際の患者さんはもっと身近なものを大切にします。「子どもたちが成人するまでの手立てを残しておかなければ」といったことを考える人も多いですし、もっとささやかなもの、例えば一日中好きなジャズを聴いていたいとか、猫と遊びたいとか、あるいは麻雀や競馬をしたいという人もいる。そうした人たちは、平凡であっても幸せな毎日を送っていたのだと思います。身の回りにこそ幸せがあるのだということを、改めて感じ直すことができた人の選択ではないでしょうか。
死の間際になってもわがままな人だっています。子どもにお金を残さずに全部使っちゃうような人がいたり、亡くなる直前まで奥さんに文句を言い続ける人がいたり。でも、そんな人も家族に許されているんです。お父さんはこんな人なんだよね、って。それはそれで幸せですよね。
かと思えばバラバラだった家族が最後に和解するなんてこともあります。父親を看取った娘さんは、お父さんのことをとても憎んでいました。浮気してお母さんを苦しめ続けたお父さんを、なんで私が介護しなきゃいけないんだと。でも病床で接するうちにだんだんと愛情を取り戻したのか、あるときを境に一八〇度変わって献身的に介護するようになりました。それは患者さんにとっての最後の役割だったのかもしれません。
結局は自分が最後にやりたいと思うことをやればいいのだと思います。「自分の死を通していのちの意味を次世代に伝える」といった視点もとても尊いものですが、それは結果論だよなという姿勢でいいのだという気もします。人はそれぞれに生き、それぞれに死んでいく。生きてきたように死んでいくんです。
ただ、「お父さん、死ぬ前に何がしたい?」という話はしづらいですよね。そこにも私たちの役割はあるのかなと思います。患者さんに「そろそろ大切な話をしたほうがいいですよ」「奥さん困ってるよ」と促すと、「そうかい?」なんて言いながら話をするようになります。家族とは別の人間がいることで、気軽に話すことができるみたいです。
末期の患者さんと一緒にお墓を見に行ったこともあります。畑仕事がご夫婦の生きがいだというので行ってみると、道の途中に先祖代々の墓地がありました。日当たりのいい、すごくきれいな場所。立派な桜並木があって、春には墓参りがてらのお花見をするそうです。患者さんが「先生、この桜は俺が手入れしたんだ。春になったら花見をしよう」と言うのを、うんうんと聞きながら、ご家族と「その頃にはお父さんいないよね」って。ご家族の目は潤んでいました。本人にも「このお墓なんですね」と聞くと、「そうだよ、墓石の裏に彫ってある唄も俺が作ったんだ」と自慢げでした。(お墓の中から)お花見できるよねって約束して、記念写真まで撮りました。
あまり深刻にならずに淡々と話せばいいのだと思います。昔はそうしたことが普段の生活で補完できていたのではないでしょうか。明治の人は「私が死んだら白装束が箪笥の何段目に入っているからね」というような会話をいつもしていた。その意味で、〝死〟が生活の一部にあったのです。いまは死の場所が病院になったことで、とても大きな、見えない恐怖になってしまっている。
ある九十代のおばあさんは、とにかく老いや死を拒否される人でした。私たちが何を言っても、「とにかく治してくれ」「現代医療なら治るはずだ」。
どれだけ説明しても、「おまえはヤブ医者だ、もっといい病院に連れて行け」。動けなくなっても眉間に皺を寄せて、治るはずだと言い続ける。しかしそんな状態が三年ほど続いたとき、急に安らかな笑顔になって皺もとれてしまったんです。まるでかわいいお地蔵様みたいに。それから二週間ほどで亡くなりました。人生には限りがあるということを、最後にやっと受け入れられたのだと思います。
ご家族には、患者さんの〝ガス抜き〟をやってあげてほしいと思います。死が近づけば、不安で、怖くて、文句を言って騒いだり、暴れ回ったりするかもしれません。しかしそうしてエネルギーを出しきったあとに安らかな時間が訪れます。それが病院で起きてしまうと錯乱と見なされて薬で抑えつけられてしまう。本人が求めるものをすべて実現できなくても、不満を聞いてあげるだけでいい。その姿勢がすごく大切です。
悔いなく死にゆくための三原則
☆最期を過ごす場所を〝自分で選ぶ〟
☆〝自分のやりたいこと〟を大事にする
☆恐怖や痛みや不安を〝我慢しない〟
死の瞬間だけではなく いのちそのものを支える
終末期の患者さんは、死への恐怖に加えて、病気の苦しさや痛みに怯えます。最後の時間を安らかに過ごしてもらうためには、この恐怖を和らげてあげることがとても大切です。がんは痛いものだから仕方ないと我慢する人もいますが、モルヒネをはじめとした薬剤などで適切に処置すれば、がんの痛みの九五パーセントは取り除けます。
モルヒネというと中毒になるイメージを持たれている人もいますが、研究の結果、病みを取る適正な量であれば依存症は心配ないということも分かっています。
しかしこうした説明をしただけでは、患者さんを安心させることはできません。私は講演などで、よく「三つのH」についてお話しします。「 Head (知 識)」、「 Hand (技術)」、そして「 Heart (温かい心)」です。 Heart はいのちに 対する哲学や文化を学び、思いやりのある態度を持つこと。この三つのどれが欠けても患者さんを救えません。
私は患者さんやご家族の前では明るく振る舞えているようです。お通夜みたいな表情だったらみんな不安になってしまいますよね。「こんにちは!」と元気に入って「大丈夫だよ!」「心配いらないよ!」と声を掛けると、皆さんの緊張がふっと軽くなるのを感じます。もともと明るい性格なのも手伝って、冗談も言うし、おどけて見せることもあります。でも患者さんと一緒に撮った写真を見ると、自分の表情にどこか寂しさや悲しさみたいなものを感じます。私は写真を撮る度にそれを確認して少し安心します。大丈夫、まだいのちの前に図々しくなってはいないと。私の顔に表れる陰りは失ってはいけないもの、いのちに対する畏敬の念だと思います。
終末期の現場で、悪ふざけとしか思えない短絡的なおどけ方をする医療者を見ることがあります。死にゆくいのちの前で悲しみに縁取られた心を持てないのならば、人の看取りに立ち会うべきではありません。もし私の写真から陰りが消えてしまったならば、この仕事を辞めるべきだとさえ思っています。死に馴れてはいけない、と。
私は「在宅ホスピス医」として紹介されることが多いのですが、内心っと違うんだけどなあと思っています。
ホスピスは私の「いのちを支える」という理念のモデルの一つです。現代医療は、細胞や遺伝子の世界、新たな薬剤の開発など、機能的な部分が注目されます。もちろんそれは素晴らしいことですが、私は臓器の構造や病気の仕組みよりも、そんな体を持った人間のいのちそのものに目が向くのです。
一組の男女が出会って私たちが生まれる確率は、宝くじの一等賞に千回続けて当たるよりもすごいことだという学者もいます。そんな奇跡的な存在が成長し、また誰かと出会って新しいいのちを紡ぐ。そして自分が紡いだ人たちに囲まれ、老いて、死にゆく。こんなダイナミックなエネルギーの流れを支えているのは何なのか、とても不思議に感じます。
人と人との関係性と、継続した時間の流れの中にいのちが存在します。患者さん自身の時間はあるところで止まってしまいますが、残された関係性にも寄り添いたい。亡くなるお父さんの前でピアニストになることを誓った娘さんは夢を叶え、私の講演会で演奏してくれました。すい臓がんで亡くなった女性のお子さんは、いま私の助手を務めてくれています。医者として、ときに教育者として、あるいは友人として、いのちそのものに寄り添いながら、「いのちを支えるものは何だろう?」の答えを探し続けているのだと思います。

