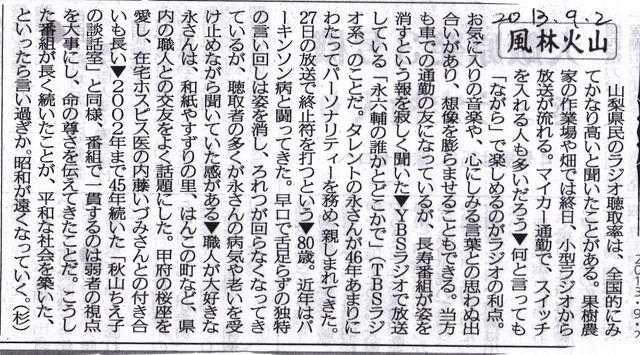「死に方」を考えたことありますか
 毎日新聞2010年11月1日(月)特集ワイドより抜粋
毎日新聞2010年11月1日(月)特集ワイドより抜粋
いかにして幸福な死を迎えるか-。このことに、かつてないほど関心が高まっている。高齢化が進み今後「多死社会」を迎えるこの国で問われる「死の質」。幸福な死とは何か。そのためにどんな準備が必要なのか。在宅ホスピスと先端医療、それぞれの現場から患者や家族の死と向き合ってきた2人の医師を訪ねた。(文 山寺香様)
JR甲府駅から車で5分ほどの場所に「ふじ内科クリニック」はある。医師である内藤いづみ院長(54)と常勤看護師3人が、末期がん患者の在宅ホスピスケアを行う小さなクリニックだ。5人が腰掛ければいっぱいになる外来の待合室で向かい合うと、内藤さんは開口一番「最近、メディアで『幸せな最期の迎え方』といった特集が増えましたが、少し安易だと感じます」と、切り出した。
95年に開業し、これまでに「自宅で死にたい」と望む約200人の最期をみとってきた。「『最期』はどう生きたかの集約です。死に方は、生き方なのです」。言葉が重い。
幸せな死を迎えられたかどうか。内藤さんは「その答えは最期の72時間(3日間)に出る」と言う。がんになると、笑ったり食べたりして家族と楽しく過ごすという日常生活が難しくなる。
「ターミナル期と呼ばれるこの3日間までを、誰が見ても何事もないような穏やかな日常にするのが私たちの仕事です。それまでに亡くなる方が死を迎える準備をし、人生を振り返って『ありがとう』『さようなら』『ごめんなさい』と言えたら、幸せな最期だと思います」
福島の医大を卒業後、東京の大学病院に勤務していた内藤さんは、命が助からないと男性患者に、内藤いづみさんは穏やかに語りかける=甲府市内で分かった途端に患者から興味を失う病院の空気になじめず、もがいた。86年、イギリス人の夫の仕事の都合で移り住んだイギリスで、ホスピスに出合う。日本ならば病院から出られない末期がんの患者が地域にとけ込み、望めば自宅で最期を迎えられることに衝撃を受けた。
09年の人口動態調査によると、自宅で亡くなったのは全体の12%。約8割が医療施設で最期を迎えた。身近から死が姿を消したことに加え、医療が進歩してアンチエージングが脚光を浴びる中、死は「敗北」であるとされてきた。
「この50年で、日本人は死生観について考えることをしなくなった」と、内藤さんは言う。しかし、納得のいく幸せな最期を迎えるためには、死と向き合い「命の哲学」を持つことが欠かせない。
「末期がんを『死に神』と表現した雑誌もありましたが、在宅ケアをする私たちは、数力月から数週間かけて人生の締めくくりができる最高に幸せな時間ととらえます。幸せな最期は人が与えてくれるものではありません。どんな最期を迎えたいのか。主体性を持って命と向き合う勇気が必要です」
最先端のがん医療に携わってきた医師は、自身の「幸せな最期」をどう考えているのだろうか。元国立がんセンター名誉総長で「妻を看取る日」(新潮社)の著書がある垣添忠生さん垣添忠生さん(69)は「(自身ががんになったら)自宅で最期を迎えたい。医学的にできることがなくなったら、食を絶って枯れ木が倒れるように死にたい。自分で食べられなくなれば点滴で水分や栄養を補給する必要はないし、延命治療は望みません」と語る。
垣添さんがこう考えるようになったのは、3年前に妻昭子さん(享年78)を亡くした体験が影響している。
昭子さんは肺の小細胞がんというたちの悪いがんに侵され、07年秋に国立がんセンターに入院した。間もなく一人で起きあがることができなくなったが、「年末年始はどうしても家で過ごしたい」と希望し、12月28日に一時帰宅が許された。垣添さんの看護を受けながら慣れ親しんだ自宅で穏やかな時間を過ごし、31日に「ありがとう」と言って亡くなった。自宅で最期を迎える希望はかなったが、垣添さんには心残りもある。
「もう助からないと分かった時点から、点滴や副作用の強い抗がん剤を使ったのはかわいそうだったと思います。体が受け付けなくなっているのに水分や栄養分を入れると呼吸が苦しくなることもある。でも、妻は私の立場を考えて治療を受けてくれたのでしょう。入院中にたった一度だけ、『こんなつらい治療を受けているのはあなたのためよ』と言いました」
昭子さんの帰宅は、垣添さんが医療機器や点滴の扱いについて担当看護師から特訓を受け、終始付き添うことで実現した。しかし、一般には家族がそのような特訓を受けられるとは限らない。患者が治療を受けていた病院と在宅医、訪問看護ステーションの連携の体制が十分でなく、末期がんの患者を在宅でみとるためのハードルは高い。垣添さんは「自宅で死にたいと思いながら実現できない人がたくさんいる。延命処置を望まない人が十分な体制がないまま自宅に帰った場合、急変時に救急車を呼べば本人の意思に反して救命処置が施される。蘇生や延命を望まない場合、文書で意思を表示しておくことも重要だ」と語る。
垣添さんに子どもはなく、自身の死後のためにすでに財産分与の遺言状を書いた。「妻と同じ78歳まで生きられれば十分だと思う。あと2、3年したら遺品整理会社と散骨会社に死後の対応を依頼するつもりです。妻の骨の半分と私の骨の半分を砕いて粉にして、私たちが好きだった中禅寺湖の浜辺にまいてほしい。
そして、跡形もなくこの世から消えてしまいたい」
家族に囲まれ、温かい雰囲気の中で「ありがとう」と言って息を引き取る。「幸せな最期」というと、こんな場面を想像する。しかし内藤さんは「家族の形は今後、加速度的に変わるでしょう。家族がいない、いるけれどもみとりまで頼めないという人が増えています」と指摘する。実際にここ10年、「死の質」に対する関心の高まりとは裏腹に、在宅ホスピスの希望者が減少しているという。
ホスピス病棟が増えたことや介護保険制度によって介護が社会化されたこと、医療の進歩などさまざまな要因があるが、家族のあり方の変化も大きいという。
内藤さんは「人生の折り返し地点である更年期を過ぎたあたりから、死がいつ訪れてもおかしくないと常にどこかで腹をくくり、医療者や家族、友人など最期の時に寄り添ってくれる人を探しておく必要がある」と話す。
幸福な死を迎えるマニュアルはない。自らの「生」と「死」に向き合うことから、第一歩が始まる。