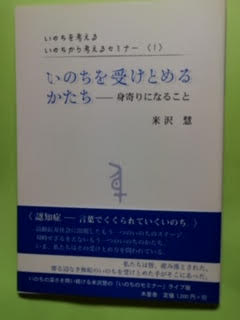往復書簡(米沢慧様)Vol.4 往
内藤いづみさま
12月、「喪中はがき」でかんがえたこと
このところ、いろいろお忙しかったようですね。元気回復できましたか。
気が付けば雪の便り、セーターを着込んだところで今年も喪中はがきがとどきはじめました。
その数も年々増えてきているようにおもいます。また、「母、享年百二歳」「父、九十八歳」と年齢が高くなる一方で同世代の人からは「妻」や「夫」の死が伝えられています。
喪中はがきといえば、
「喪中につき、年頭の挨拶は失礼させていただきます」
「……年末年始のご挨拶はご遠慮申し上げます」
と、どれもが印刷され、一般に形式も整っており破綻もない儀礼的なものです。
1年に1度の消息が年明けを前にして届くものですが、賀状とはちがいつい身構えてしまいがちです。
なかには、心にしみる思いがけないことばにであい、しばらく保存しているものがあります。
〈拝啓 今年も残り少なくなりましたが、お変わりなくおすごしのことと拝察申し上げます。私事ですが、今年5月31日、母○○が帰らぬ旅立ちをいたしました。いつものように、夕食もそろそろ終わろうかという時でした。母はふっと、蝋燭の火が消えるように、家族の眼前で逝ってしまいました。
私たちがそばについていながら、と自責し、90歳をこえてなお、母がいつまでも、ともに生きているものと疑わなかった、わが身のおろかさを思いました。
それから半年、そう願わなくとも、時間はすこしずつ癒しをもたらして、今年もほどなく暮れ、新しい年がやってまいりますが、このたびは喪中のならいに従い、新年を寿ぐご挨拶を遠慮させていただくことにしました。……〉
〈哀しいご報告をさせていただきます。妻、Mが12月10日に急逝いたしました。享年55歳でした。今、私たち残された家族は、深く辛い別離のなかで、ただただ呆然としております。妻の命が「いのち」として私たちの心の奥深くにしみわたり、悲しみと共生できる日を静かに待ちたいと考えております。
妻は、はにかみやで派手なことを嫌う人でもありました。そこで妻の意にそう形で内輪にて葬儀をさせていただきました。妻そして私たち家族に賜りましたご厚情を深く感謝いたします。幸いにして長女△△、長男▲▲が私を支えてくれています。31年間の夢のような結婚生活を送らせてくれた妻に感謝しつつ、ご報告させていただき、新年のご挨拶をご遠慮させていただきます。……〉
亡くなった方と面識があるわけではありませんが、それぞれに胸を打たれて、返事を出すすべもないまま、いまも引き出しに納まって残っています。
ここには、新年を迎えることよりも、ともに生きた歳月を明け渡すことのほうがつらいこと。けれど「少しずつ癒しをもたらしてくれる」という時間と、「悲しみと共生できる日を静かに待ちたい」という祈りにちかいおもいも伝えられています。
年があらたまり、やがて安息安寧の日々を伝える賀状をまつのです。その次の年にはきっと賀状が届きます。
喪中。死亡した人を追悼する礼。このことばが喚起するものはなんでしょうか。
「歳月」ということばです。亡くなった人との親密な歳月への思いです。
茨木のり子詩集に『歳月』があります。
この詩集は生前発表する意思がなかったとおもわれます。夫と暮らした25年という歳月を、詩人が亡くなる日(2006年死去・80歳)までの31年間、密やかに書き継ぎ保存されてあった39編で、すべてが夫との暮らしにふれた作品です。
表題となった「歳月」をあげてみます。
《真実を見きわめるのに
二十五年という歳月は短かったでしょうか
九十歳のあなたを想定してみる
八十歳のわたしを想定してみる
どちらかがぼけて
どちらかが疲れはて
あるいは二人ともそうなって
わけもわからず憎みあっている姿が
ちらっとよぎる
あるいはまた
ふんわりとした翁と媼になって
もう行きましょう と
互いに首を締めようとして
その力さえなく尻餅なんかついている姿
けれど 歳月だけではないでしょう
たった一日っきりの
稲妻のような真実を
抱きしめて生きぬいている人もいますもの》
詠むかぎりにおいて、歳月とは亡き夫とのかけがえのない二五年間の追慕ですが、詩篇の内実はそれだけではありません。「九十歳のあなたを想定してみる/八十歳のわたしを想定してみる」という夫の没後の歳月(31年)と残された自らの暮らしが重なっていますね。つまり、喪に服すのではなくて、夫との共生のなかにその後の年月が育まれています。歳月は過去形としてあるのではなく、老いを支え、生きていくおだやかな安寧の日々のなかに埋め込まれているのがわかります。
師走に届く喪中はがきといえば、お定まりの「喪中につき、年末年始のご挨拶はご遠慮申し上げます」。けれど、その一行のなかに「いのち」の物語が秘められていることだけはまちがいありません。
こんなことをあらためて抱いたのも、私自身さきごろ学生時代からの友人を亡くし、一人残されたその母御(94歳)から同様のはがきが届いたことと関係しています。
けれど、友の死は身内の抱く哀しみ、喪に服すというかたちでは収まりがきかない悼みの感覚です。先日もある人から「友だちの死はジャブのように少しずつ効いてくるよ」と聴いたことがあります。この悼みはどう表現したらいいのか、どう受けとめたらいいのか。そんな自問自答に応えるように最近ある本に出合いました。哲学者鶴見俊輔(86)著の『悼詞』(SORE)という本です。
この本はざっと400頁、一冊まるごと弔辞や追悼文でうめつくされています。鶴見俊輔といえば、戦後の思想界をリードしてきた重鎮の一人です。その交流の広さから採りあげられた人たちの顔ぶれは125人。銀行家の池田成彬(50年没)からマンガ家の赤塚不二夫(80年没)まで、作家、学者にとどまりません。同時代を生きたそれぞれの仕事から人柄まで感傷のない、たしかな悼詞の連鎖になっています。
ここで悼詞とは単に人の死をいたみ弔う詞、というのとはちがうのです。本書冒頭にあった次の詩篇がその意を伝えているようにおもいます。
《人は死ぬから えらい
どの人も 死ぬからえらい。
わたしは 生きているので
これまでに 死んだ人たちをたたえる。…》
そうだ、大事なことを忘れていたという思いでした。人は誰もが死ぬことは知っています。いつか死ぬと思っていますが、目の前で死んでいくのはいつも私以外のだれかです。この哀しみに対して「わたしは (まだ)生きているので これまでに 死んだ人たちをたたえる」とつぶやいてみます。すると、悼詞は喪ったこと以上に、生の意味をたしかなものにしてくれそうな気がします。念のために補足しておけば、本書あとがきで「私がつきあいの中で傷つけた人のことを書いていない」という鶴見さんの自省が述べられていることです。つまり、悼詞には、人はどこかでだれかを傷つけることなく生きていくことはできないという自戒も含んでいるということです。
こうした感想を臨床の場面に移して考えるとどうなるか、ここでも最近出た『詩と死をむすぶもの』(朝日新書)から教えられたことがありました。この本は詩人(谷川俊太郎)とホスピス医(徳永進)の往復書簡ですが、冒頭の口絵写真「野の花診療所の近くを流れる千代川の河原にやってきた野の花旅団のご一行さま」に感銘を受けてしまい、壁に貼りつけてしまいました。このあかるさは、このやすらぎとおだやかさは…。
この本については内藤いづみさんの感想を待ちたいですね。キューブラー・ロスについても語られています。
さて、今年さいごの便りにもうひとつ、92歳の女性の方から届いた転居通知のはがきを紹介したくなりました。
〈私は92歳の誕生日を前に夫とともに、××不動尊近くの老人ホーム○○に居を移し、ここを終の住処と定めました。
住みなれた△△の家を離れるのは淋しいものでありますが、昨年11月頃ころんで右大腿骨を折ってしまい、以来、自力歩行がかなわずやむなくこのような選択となってしまいました。
ただ、本意ではないとはいえ、ホームのくらしに不満はありません。自分の身一つままならぬ毎日ですが、介護者の助けを得て、これからの一日一日を大切に生きていこうとおもいます。どうかあなたさまにおかれましても、御身ご自愛くださいますように。〉
この方は3年前私家版の表現歌集を贈ってもらったSさん、市井のひとです。90歳を前にして、これまで折にふれて書かれた短歌や俳句に詩、小説・散文を一冊にまとめたもので、
〈老い盛り果てて背丈のちぢみ来ぬ春光さけて日陰を歩む〉
〈物みなに影ありときく目覚むれば昼寝の夢は影絵のごとし〉
など、印象にのこっていましたが、
とくに気に入ったのが歌集の表題、『呼吸(いき)ととのへり』でした。
新年がおだやかな年でありますように。
米沢慧